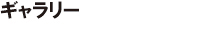レトロ門司の歴史的建造物
門司港地区
■ 門司港地区
▼ レトロ門司港の景色


▼ 門司港駅
1988年、駅舎として全国初の国指定の重要文化財。ネオ・ルネサンス様式。ドイツ人技師ヘルマン・ルムシュッテル監修下で1914年(大正3年)建造の木造駅舎。イタリアのテルミニ駅を参考にしたという美しい左右対称の木造建築で、青銅製の手水鉢や水洗式トイレ、大理石とタイルばりの洗面所、御影石の男性用小便器など、当時としては非常に珍しい重厚かつモダンな作りである。現役の駅舎が重要文化財に指定されるのは非常に珍しく国内最高の駅舎と言われる。
門司駅(現門司港駅)は,九州鉄道の起点駅として明治24年(1981年)4月1日に開業したが、大正3年に場所を200mほど移し、現在の場所に建て替えられた。その後、昭和17年(1942年)関門鉄道トンネルの開通に伴い,同年4月トンネル口にあたる大里駅が門司駅に改称され,これまでの門司駅は門司港駅となった。昭和63年12月19日(文部省告示第127号)に重要文化財に指定されて以降、小規模な修理が施されたものの、門司地区の発展に伴い手狭となったことや、老朽化への対応や耐震補強が必要になったため、平成24年7月より国庫補助金事業として全面的に改築することとなった。
2012年(平成24年)9月から駅舎の保存修理工事に着手。素屋根(工事中の駅舎を覆う仮設の大屋根)の設置と建物の分解・部材調査、構造体再組立て、構造補強工事などを経て、11月10日に先行開業(駅機能切替え)した後、2019年3月にグランドオープンを迎える。
駅舎保存修理工事は、創建時(大正3年)の華麗な姿に復元することを基本方針として、約6年の年月を要したが、駅舎は中央に門構えの意匠が復活。ペンキ塗りだった外壁は石張り風とし、銅やスレートの屋根は天然の石を使って"化粧直し"された。みどりの窓口は旧1、2等待合室、さらに1階の旧3等待合室など建設当時のデザインが再現され、当時の暖炉も設置された。コンコースでは旧出札室窓口に自動券売機が設置され、構造補強を兼ねたエレベーターが新設された。駅の2階には洋食レストラン、1階にはカフェも入居する。駅前広場も3月に同時オープンする。
門司駅(現門司港駅)は,九州鉄道の起点駅として明治24年(1981年)4月1日に開業したが、大正3年に場所を200mほど移し、現在の場所に建て替えられた。その後、昭和17年(1942年)関門鉄道トンネルの開通に伴い,同年4月トンネル口にあたる大里駅が門司駅に改称され,これまでの門司駅は門司港駅となった。昭和63年12月19日(文部省告示第127号)に重要文化財に指定されて以降、小規模な修理が施されたものの、門司地区の発展に伴い手狭となったことや、老朽化への対応や耐震補強が必要になったため、平成24年7月より国庫補助金事業として全面的に改築することとなった。
2012年(平成24年)9月から駅舎の保存修理工事に着手。素屋根(工事中の駅舎を覆う仮設の大屋根)の設置と建物の分解・部材調査、構造体再組立て、構造補強工事などを経て、11月10日に先行開業(駅機能切替え)した後、2019年3月にグランドオープンを迎える。
駅舎保存修理工事は、創建時(大正3年)の華麗な姿に復元することを基本方針として、約6年の年月を要したが、駅舎は中央に門構えの意匠が復活。ペンキ塗りだった外壁は石張り風とし、銅やスレートの屋根は天然の石を使って"化粧直し"された。みどりの窓口は旧1、2等待合室、さらに1階の旧3等待合室など建設当時のデザインが再現され、当時の暖炉も設置された。コンコースでは旧出札室窓口に自動券売機が設置され、構造補強を兼ねたエレベーターが新設された。駅の2階には洋食レストラン、1階にはカフェも入居する。駅前広場も3月に同時オープンする。








門司港駅
▼ 旧門司税関



旧門司税関
▼ 旧大阪商船ビル



旧大阪商船ビル
▼ 旧門司三井倶楽部

旧門司三井倶楽部 本館正面


旧門司三井倶楽部 本館
付属屋、倉庫(手前)
▼ 大連記念館



大連記念館
▼ 旧料亭・三宜楼

旧料亭・三宜楼


2階の「百畳間」
▼ 鉄道記念館



九州鉄道記念館
▼ 門司電気通信レトロ館


門司電気通信レトロ館
▼ 旧門鉄ビル


旧門鉄ビル
▼ 門司港ホテル





門司港ホテル
▼ 出光美術館



出光美術館
▼ レトロハイマート



レトロハイマート
▼ 海峡ドラマシップ



海峡ドラマシップ
▼ 関門海底国道トンネル



レトロ門司の歴史的建造物
▼ 甲宗八幡神社 平知盛菩提



甲宗八幡神社 平知盛菩提
門司・大里地区
■ 門司・大里地区
▼ 戸ノ上神社



戸ノ上神社