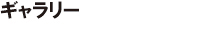山月園 部屋からの眺め





旧岩崎別邸和館








桃の花咲く 山月園



南天の実成る 山月園

関東最初の水力発電所「箱根電燈発電所」設置跡 (本館玄関横)







明治の元老・山縣有明の茶室「暁亭」を本館に移築保存 電力王・松永安左衛門もこの茶室を愛した


世界屈指の山岳鉄道:小田原馬車鉄道・電気鉄道湯本駅跡 (今日の箱根登山鉄道の前身)
■ 「電力王」「電力の鬼」と呼ばれた松永安左エ門
明治8年、長崎県壱岐島の旧家の長男に生まれ、14歳で福沢諭吉を慕い慶応義塾へ入塾。石炭商で大儲けし、北九州での電力に目を向け九州電気株式会社を設立、電力業経営へと注力する。東邦電力(九州電力の前身)を中心に、東北電気、東京電力など約100社を支配下に置き、昭和26年、電力技術研究所を設立(のちに電力中央研究所に改組)。電力設備の近代化と電源開発を推進し、昭和46年、96歳で亡くなるまで電気事業の世界に、そして経済界、産業界、政界に多大の影響を与え続け、近代日本の発展を導いた。とくに、戦後日本の高度経済成長の礎となる電気事業の分割民営化を成し遂げ、「電力王」「電力の鬼」と呼ばれた。勲一等瑞宝章叙勲者。
古美術収集家、茶人としても知られ、益田孝(「鈍翁」・三井コンツェルン設立者・男爵)、原富太郎(「三渓」・明治〜大正前期の実業家。富岡製糸場所有・絹貿易の富で横浜復興)と共に、「耳庵」の号を持つ近代日本三茶人の一人。箱根における登山電車の運行のためには水力発電所の建設が必須であったが、とくに湯本〜強羅間の電気鉄道建設(小田原電気鉄道KK、現在の箱根登山鉄道)では強羅開発のときに小田原の掃雲台に別邸を持つ益田孝や益田の義兄弟の明治元老・山縣有朋、政治家・実業家の井上馨、福澤諭吉の婿養子で大同電力の初代社長・福澤桃介らと尽力している。昭和21 年(1946年)に住居を小田原に移す。収集した古美術品の一部は東京国立博物館に寄贈し、残りは自宅庭に建てた記念館「松永記念館」に収蔵したが、現在は福岡市美術館や京都国立博物館などに分蔵されている。
明治8年、長崎県壱岐島の旧家の長男に生まれ、14歳で福沢諭吉を慕い慶応義塾へ入塾。石炭商で大儲けし、北九州での電力に目を向け九州電気株式会社を設立、電力業経営へと注力する。東邦電力(九州電力の前身)を中心に、東北電気、東京電力など約100社を支配下に置き、昭和26年、電力技術研究所を設立(のちに電力中央研究所に改組)。電力設備の近代化と電源開発を推進し、昭和46年、96歳で亡くなるまで電気事業の世界に、そして経済界、産業界、政界に多大の影響を与え続け、近代日本の発展を導いた。とくに、戦後日本の高度経済成長の礎となる電気事業の分割民営化を成し遂げ、「電力王」「電力の鬼」と呼ばれた。勲一等瑞宝章叙勲者。
古美術収集家、茶人としても知られ、益田孝(「鈍翁」・三井コンツェルン設立者・男爵)、原富太郎(「三渓」・明治〜大正前期の実業家。富岡製糸場所有・絹貿易の富で横浜復興)と共に、「耳庵」の号を持つ近代日本三茶人の一人。箱根における登山電車の運行のためには水力発電所の建設が必須であったが、とくに湯本〜強羅間の電気鉄道建設(小田原電気鉄道KK、現在の箱根登山鉄道)では強羅開発のときに小田原の掃雲台に別邸を持つ益田孝や益田の義兄弟の明治元老・山縣有朋、政治家・実業家の井上馨、福澤諭吉の婿養子で大同電力の初代社長・福澤桃介らと尽力している。昭和21 年(1946年)に住居を小田原に移す。収集した古美術品の一部は東京国立博物館に寄贈し、残りは自宅庭に建てた記念館「松永記念館」に収蔵したが、現在は福岡市美術館や京都国立博物館などに分蔵されている。